はじめに
「お金の勉強って何から始めたらいいの?」
そう感じている方、多いのではないでしょうか。
学校では教えてくれない「お金の知識」。
しかし、社会人になってからの生活、将来設計、老後の安心を考える上で、避けて通れないテーマです。
この記事では、初心者でも今日から始められる「お金の勉強法」を、わかりやすく・体系的に解説します。
読めば、支出の見直し方・貯め方・増やし方・守り方までがしっかり理解できるようになります。
なぜ「お金の勉強」が必要なのか
お金の知識がないまま生活していると、次のような問題が起こりがちです。
- 無駄な支出が多く、なかなか貯まらない
- 老後資金や教育費など、将来が漠然と不安
- 投資や制度の仕組みを知らずに損をしている
逆に、お金の知識を身につけると――
- 収支をコントロールできる
- 貯蓄や投資で「お金が働く」仕組みを理解できる
- 不安より「安心感」が増す
つまり「お金の勉強=生き方を整える」ことなのです。
ステップ1:まずは「現状を知る」ことから始めよう
1.1 家計簿で“見える化”する
最初のステップは、「収入と支出を把握すること」。
これは、どんなに稼いでいても、どんな節約法を知っていても、避けて通れません。
おすすめは、家計簿アプリの活用。
たとえば「マネーフォワードME」「Zaim」「Moneytree」など。
口座やカードを連携すれば、自動で記録できるので続けやすいです。
手書きでも構いません。重要なのは「お金の流れを可視化すること」です。
1.2 支出を分類して整理する
支出は、大きく次の3つに分けてみましょう。
- 固定費(家賃・保険・通信費など)
- 変動費(食費・交際費・交通費など)
- 投資・貯蓄(未来に向けたお金)
この3分類にするだけで、どこに無駄があるかが見えてきます。
ステップ2:「貯める」仕組みを作る
2.1 先取り貯蓄が最強
「残ったら貯める」ではなく、「先に貯める」。
これが貯金を続ける最大のコツです。
給料が入ったら、すぐに一部を貯蓄口座に移す。
たとえば「手取りの10〜20%」を目安に、先取りしておくとよいでしょう。
貯金専用口座を作ると、日常の支出と切り分けやすくなります。
2.2 固定費を見直す
固定費は、一度見直すだけで毎月の支出が大きく変わる部分です。
具体例として――
- スマホ:格安SIMに乗り換える
- 保険:内容が重複していないかチェック
- サブスク:使っていないサービスを解約
これだけでも、月5000〜1万円の削減が可能です。
年間では6万円〜12万円の節約。これを貯蓄に回せば、かなりの違いです。
2.3 緊急資金を確保
急な出費に備えて「生活費3〜6ヶ月分」の緊急資金を確保しましょう。
初心者なら、まず「1ヶ月分」を目標にしてもOK。
いざという時に安心です。
ステップ3:「増やす」ための知識を身につけよう
貯める習慣ができたら、次は「お金を働かせる」ステップへ。
つまり「投資」や「運用」です。
3.1 投資の基本3原則
投資で大切なのは次の3つです。
- 長期投資(時間を味方にする)
- 分散投資(リスクを減らす)
- 低コスト投資(手数料を抑える)
この3つを守るだけで、初心者でも安定的に資産形成ができます。
3.2 NISAから始めよう
日本では「新NISA(少額投資非課税制度)」が2024年からスタートしました。
投資で得た利益が非課税になるお得な制度です。
つみたてNISAでは、毎月定額を自動で投資できるので、初心者にも最適。
おすすめは「全世界株式」や「S&P500」などのインデックスファンド。
リスクを分散しながら、世界経済の成長に乗れます。
3.3 少額から始めてOK
「投資はお金持ちのもの」と思う人もいますが、今は100円から始められる時代。
楽天証券・SBI証券・マネックス証券などで、積立設定すれば、ほぼ放置でもOKです。
ステップ4:「守る」知識を身につける
お金を増やすだけでなく、「守る」ことも重要です。
ここでは、税金・保険・年金の基本を押さえましょう。
4.1 税金の仕組みを知る
税金には、所得税・住民税・消費税・相続税など、さまざまな種類があります。
特に会社員は「源泉徴収」で自動的に引かれているため、意識しづらいですが、
控除制度を理解すると、節税できることもあります。
代表的な制度:
- ふるさと納税
- 医療費控除
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
これらをうまく使うことで、手取りを増やすことが可能です。
4.2 保険の基本を押さえる
保険は「万が一に備える」ものですが、入りすぎている人が多いのも事実。
医療保険・がん保険・生命保険など、重複していないか見直しましょう。
独身か家族持ちか、子どもの有無によっても最適な保険は変わります。
「最低限の保障+貯蓄型は避ける」が原則です。
4.3 年金・社会保障も確認
国民年金・厚生年金など、将来受け取れる金額を知ることは重要です。
日本年金機構の「ねんきんネット」で簡単に確認できます。
また、企業型DC・iDeCoを利用すれば、老後資金を効率よく準備できます。
ステップ5:「習慣化」して続けるコツ
知識を得ただけでは意味がありません。
日々の行動を変え、習慣にすることで初めて成果が出ます。
5.1 毎月の「お金会議」を開く
月に1回、15分だけ時間をとって「お金会議」をしましょう。
- 今月の支出はどうだった?
- 目標に近づいた?
- 来月はどこを改善する?
この「振り返り習慣」を続けると、自然とお金の意識が変わっていきます。
5.2 目的を明確にする
「なぜお金を貯めたいのか?」をはっきりさせましょう。
旅行資金、マイホーム、将来の安心など、目的が明確だと継続できます。
5.3 自動化で続ける
人は「意思の力」で続けるのが苦手。
だからこそ、「自動積立」「自動送金」「サブスク削減」など、仕組み化がカギです。
よくある初心者の悩みと解決策
| 悩み | 解決策 |
|---|---|
| 何から始めればいいか分からない | まずは家計簿アプリで収支を見える化する |
| 貯金が続かない | 給与日に自動で先取り貯金を設定する |
| 投資が怖い | 少額から・長期・分散で始める(NISA活用) |
| 保険が複雑で分からない | 必要最低限+無料相談で見直す |
| 続けるのが苦手 | 月1の振り返りタイムを設けて習慣化する |
おすすめ書籍・教材
お金の勉強を体系的に学びたい方に、初心者向けのおすすめ本を紹介します。
1. 『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』
著:ニック・マジューリ
内容:自動積立の大切さ、時間を味方にする思考法を学べる。
価格:1,870円
2. 『金持ち父さん 貧乏父さん』
著:ロバート・キヨサキ
内容:お金の考え方・働き方の根本を学べる世界的ベストセラー。
価格:1,760円前後
3. 『本当の自由を手に入れる お金の大学』
著:両学長(YouTuber)
内容:貯める・稼ぐ・増やす・守る・使うの5ステップを体系的に解説。
価格:1,540円
初心者が最初に読む本として最も人気があります。
Q&A:お金の勉強に関するよくある質問
Q1:貯金がゼロでも始められますか?
→ もちろんOKです。まずは「1ヶ月の収支を記録」するだけで立派なスタートです。
Q2:投資って必ずやるべき?
→ 義務ではありません。貯金が安定してから、余裕資金で少しずつ始めましょう。
Q3:どれくらい勉強すればいい?
→ 数ヶ月で基礎は身につきます。その後は実践と振り返りで知識を深めていきましょう。
Q4:難しい数字が苦手です…
→ 大丈夫です。今はアプリが自動でグラフ化してくれる時代。感覚的に学べます。
まとめ:今日からできる3つのアクション
- 今月の支出をすべて記録する
→ 見える化が最初の一歩。 - 固定費を1つ見直す
→ スマホ・保険・サブスクを点検。 - 本を1冊読む
→ お金の勉強は「知ること」から始まります。
この3つを今日実行できたら、あなたはもう「お金の勉強」を始めています。
焦らず、コツコツと、楽しみながら学んでいきましょう。
終わりに
お金の勉強は「数字の話」ではなく、「自分の人生の話」です。
正しい知識を持つことで、不安が減り、人生の選択肢が増えます。
最初の一歩を踏み出せば、きっとお金との付き合い方が変わっていくはずです。
今日が、あなたの「お金の教養」のスタートになりますように。
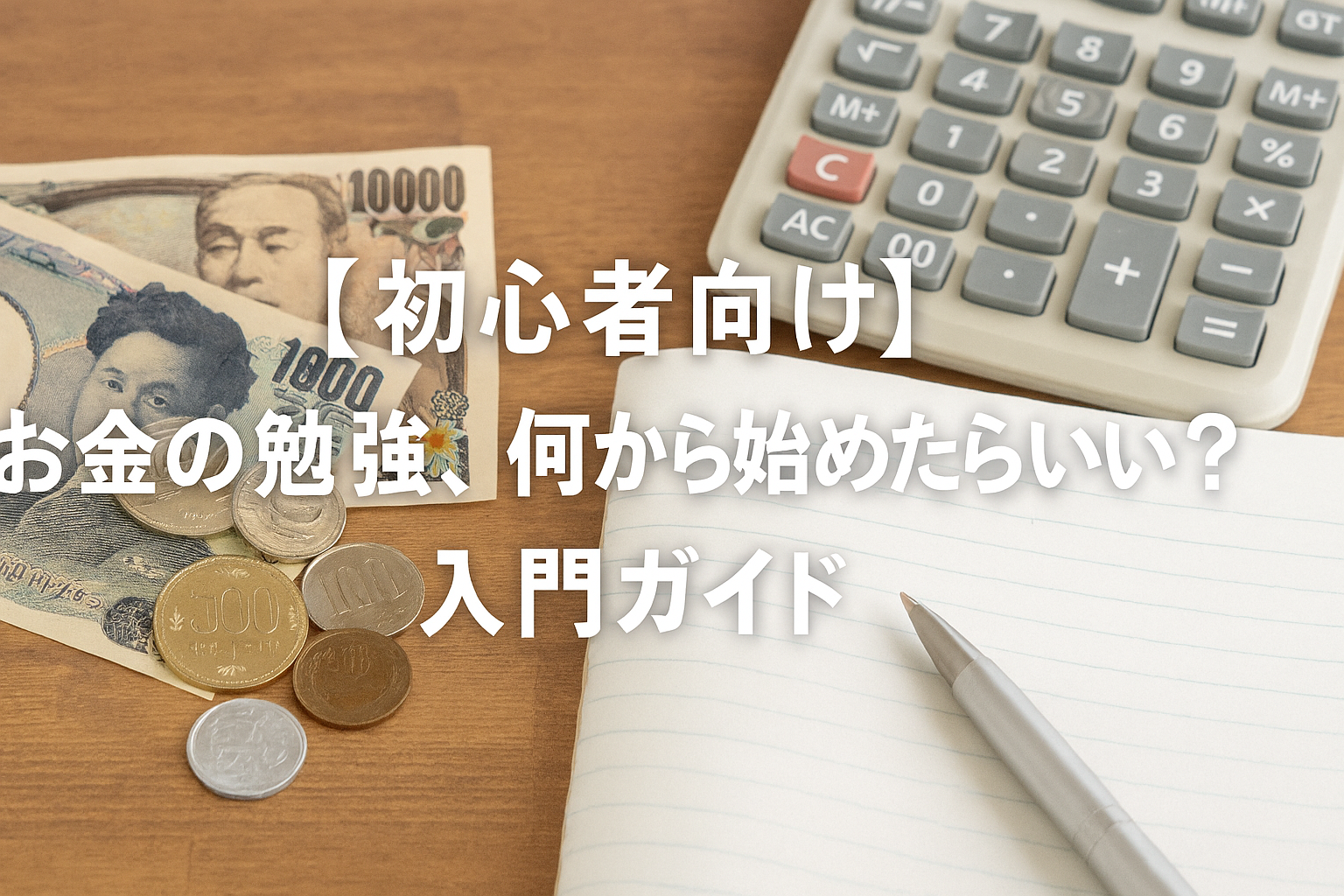





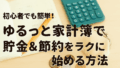
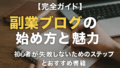
コメント